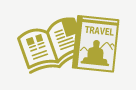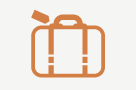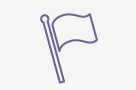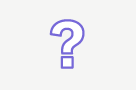[光明寺]鎌倉最大級の山門を構える浄土宗大本山

浄土宗の大本山、光明寺について
材木座にある浄土宗のお寺「光明寺」。正式名称は「浄土宗大本山 天照山蓮華院 光明寺」といいます。
開基は、鎌倉時代の4代執権の北条経時公。1240(仁治元)年、経時公が佐助ヶ谷(現在の鎌倉市佐助)に蓮華寺を建て、然阿良忠(記主禅師)を迎えて開山しました。後年の1243(寛元元)年、蓮華寺を現在の地に移して光明寺と改めたのが始まりとされます。
佐助1丁目にある蓮華寺址の石碑
光明寺は、経時公をはじめとする歴代執権の帰依を受け大寺院として発展し、「関東総本山」として念仏道場の中心となり、その役目を果たしました。また、1495(明応4)年には、御土御門天皇の勅命により国家鎮護などを祈願する「勅願寺」となり、これに併せて京都で行われていた「十夜法要」が光明寺でも行われるようになりました。十夜法要は「お十夜」「十夜講」「十夜念仏」などとも呼ばれ、500年以上に経過した今も、人々の安らかな暮らしと豊作を祈る行事として継承されています。光明寺では、古式に従い、引声阿弥陀経・引声念仏によって行われ、昼夜にわたり参拝の人々で賑わっています(=写真)。

境内に露店が並び、昼夜問わず賑わう十夜法要
「令和7年 十夜法要について」
2025年10月12日(日曜日)、13日(月曜日・祝日)、14日(火曜日)
[日程]
●10月12日(日)
17時~十夜開白法要
●10月13日(月・祝)
10時~晨朝法要
11時20分~施餓鬼・祈願会
12時30分~説教
13時30分~練行列出発
14時~日中法要
15時40分~施餓鬼・祈願会
16時30分~説教
17時30分~稚児礼讃舞
18時~初夜法要
●10月14日(火)
10時~晨朝法要
11時20分~施餓鬼・祈願会
12時30分~説教
13時30分~練行列出発
14時~日中法要
15時40分~施餓鬼・祈願会
16時30分~説教
17時30分~稚児礼讃舞
18時~結願法要
★露店については、13日(月・祝)、14日(火)の両日開催
*13日の午前中、準備が整い次第順次開催予定。露店は両日共に21時まで。

山門特別公開
- 日程:令和7年10月13日(月曜日・祝日)、14日(火)に山門特別公開を行います。
- 時間:10時から16時(15時30分最終受付)
- 予約不要 拝観料:500円
※自転車は必ず所定の駐輪場に置いて下さい。
※近隣の道路に駐車・駐輪することは交通の妨げになりますので絶対におやめ下さい。
▶詳細は、光明寺HP<外部リンク> もしくはお電話(0467-22-0603)にて
浄土宗 開宗850年記念事業~大殿(本堂)令和の大改修~

(工事前の大殿)
光明寺では、2019(令和元)年11月から、浄土宗開宗850年慶讃記念事業として、重要文化財の大殿(本堂)の保存修理工事を行っています。現在は境内の開山堂が仮本堂となっており、阿弥陀如来および諸尊像は開山堂に移っています。
光明寺の大殿は、徳川家や磐城平藩(のち延岡藩)内藤家の庇護のもと、1698(元禄11)年に建立されました。威風堂々とした風格漂う大堂は、1999(平成11)年に国の重要文化財に指定されましたが、建立から300年以上が経過し、老朽化が著しいため、今回の”令和の大改修”として2029年までの長期にわたる事業に着手しています。
(2021年4月の本殿工事風景)
工事が進む中、2021年春には、大殿内の本尊が安置されている厨子から左右一対の天女の壁画が発見されました。壁画は金箔が施された色鮮やかな状態で見つかり、大変な話題となりました。現在、専門家による分析中ですが、今後、大殿の工事風景も含め、展示できる機会を検討しています。
眺望抜群の山門拝観
光明寺の象徴でもある山門(三門)は、鎌倉最大級の規模を誇り、大本山に相応しい荘厳な造り。現在の山門は、1847(弘化4)年のもので、間口約16m、奥行約7m、高さ約20mという大きさ。山門前で見上げると、後花園天皇の直筆と伝わる立派な扁額(=写真)が掲げられおり、往時の威光を感じることができます。
山門は2階に上がり特別拝観することもできます。団体参拝、もしくは3月下旬の観桜会、10月の十夜法要などの機会に特別参拝ができますので、もうひとつの光明寺の魅力を体感してみてはいかがでしょう。

2階には、釈迦三尊、四天王、十六羅漢が祀られており、山門南側からは鎌倉の海が一望できる絶好のロケーションが楽しめます。東は鎌倉時代に東国の貿易の拠点として開発された日本最古の築港遺跡「和賀江島」、西は新田義貞が鎌倉攻めの際に海中に宝剣を投げたとされる「稲村ヶ崎」や「江の島」が望めます。
| 拝観冥加料 / お一人様500円(拝観は20名様以上) | |
| 拝観時間/ 午前10時から午後4時まで(1団体1時間以内) *ただし、寺の都合により拝観できない場合もあり。電話でお問い合わせを |
見どころ満載!光明寺さんぽ
- ”ハス池”で有名な「記主庭園」

江戸幕府の作事奉行として名古屋城の天守閣などの工事を担った小堀遠州風の浄土庭園は、開山ゆかりの「記主庭園」。庭園内のハス池は、夏に可憐な紅蓮が池一面をピンクに染め、「観蓮会」なども催され、多くの観光客が訪れることで知られています。
また、回廊から望める正面の建物は大聖閣(たいしょうかく)といい、宗祖法然上人800年大御忌を機に建てられたものです。お堂の二階には阿弥陀三尊が安置され、神聖な堂内で精進料理を食べることもできます(要予約<外部リンク>)。
- 三尊五祖の石庭 (現在、本堂修理に伴い、拝観が出来ません)

浄土宗の教えの流れを表現している石庭。三尊とは、極楽浄土の阿弥陀仏とその脇士たる観音・勢至の二大菩薩を表し、五祖は浄土教を説法流布された釈尊(印度)、善導(中国)、法然、鎮西、記主の浄土宗五大祖師を示します。この三尊五祖が、庭園の中に石で表現されています。庭園全体の構図は、煩悩の多いこの世(此岸)と救われていく彼の岸(彼岸)を示しています。5月にはサツキが見頃を迎え、石庭を彩ります。
- 富士山が一望できる天照山(かながわの景勝50選)

光明寺の裏山の天照山は、富士山の景勝地としても知られ「かながわの景勝50選」に選ばれています。空気の澄んだ日にこの高台に登ると、光明寺、由比ガ浜、稲村ヶ崎、富士山が一直線に見渡せます。また、開山の良忠上人御廟や北条経時公の墓所があります。
- 鎌倉アカデミアの碑
戦後間もない昭和21年5月、光明寺を仮校舎として「鎌倉アカデミア」が開校しました。学長に哲学者・三枝博音、教授陣には作家の高見順や歌人の吉野秀雄らを迎え、「自由大学」「寺子屋大学」などと称されました。既成概念にとらわれない教育方針は多くの若き才能を輩出。作家の山口瞳をはじめ、作曲家のいずみたく、タレントの前田武彦等は鎌倉アカデミアで学んだ卒業生です。

山門前での「鎌倉アカデミア」集合写真

当時のアカデミア学生の活動風景
創立から4年後、財政難から惜しくも廃校となりましたが、公開授業やマンツーマンの課外授業など、自由な気風に満ちた先駆性は今日あらためて見直されている。開校から半世紀を経た平成8年には、その足跡を残すため、境内に記念碑が建立されました。「ここに鎌倉アカデミアありき」と記された碑は、「教育の原点」を示すシンボルでもあります。

- 子狐を助けた良忠上人ゆかりの社
境内に良忠上人ゆかりの「繁栄稲荷大明神」があります。良忠上人は光明寺を開くまで住んでいた佐介ヶ谷で、子狐を助けたことがあったという。上人の夢に親狐が現れ、子狐を助けたお礼とともに薬種袋を残しました。当時、鎌倉で悪病が流行した際、良忠上人はこの薬種を蒔くと三日のうちに成長。薬草を服用すると病魔がたちまち退散したという伝承が残されています。ちなみに、この薬草は鎌倉の海岸でも見られるハマダイコンではないかとも言われています。後年、稲荷大明神を勧進し、病魔退散、豊漁、家業繁栄を祈念しています。
- 内藤家のお墓
江戸初期に光明寺の檀家となった陸奥国磐城、日向延岡藩主の内藤家。境内には高さ3メートルを超す宝篋印塔や五輪塔など、100以上の石塔が並ぶ墓所があります。このように大規模な大名の墓所が一ヶ所にまとまっているのは全国的に珍しく、鎌倉市指定の史跡にも指定されています。寺務所に声をかければ、通常時でも参拝が可能となっています。
国宝指定の寺宝「当麻曼陀羅縁起絵巻二巻」は、1675(延宝3)年に内藤家から寄進されたもの(鎌倉国宝館に保管)。作品は、奈良当麻寺に所蔵される「当麻曼陀羅図」の由来を描いたもので、鎌倉時代の絵巻の優品として名高い絵巻として知られています。

霊場について
「東国花の寺 鎌倉二番」
「鎌倉三十三観音・第十八番・関東七観音霊場 如意輪観世音」
「鎌倉二十四地蔵尊・第二十二番 延命地蔵尊」
[番外編]少し足をのばして日本最古の港、和賀江嶋へ
光明寺から材木座海岸に出ると、逗子の小坪方面に遠浅に浮かぶ石群が見えます。これが現存する日本最古の築港遺跡として国の史跡に指定される「和賀江嶋」です。満潮時には島のように見え、干潮時には歩いて渡れるほどに浮かび上がります。歴史書の「吾妻鏡」によれば、鎌倉時代初期に勧進僧の往阿弥陀仏という方が執権北条泰時の許可を得て造ったものとされています。悠久の時を経て佇む鎌倉時代の港…ここから見る夕景は息をのむ美しさです。ぜひ訪れてみてはいかがでしょう。
基本情報
| 住所 |
〒248-0013 |
|---|---|
| アクセス |
[車] [公共交通機関] ▶グーグルマップを開く<外部リンク> |
| 開門時間 | 開門:午前6時/閉門:午後5時(4月1日より10月14日まで) 開門:午前7時/閉門:午後4時(10月15日より3月31日まで) |
| 参拝料 | ご志納 |
| 電話 | 0467-22-0603 |
| 公式サイト | http://komyoji-kamakura.or.jp/<外部リンク> |
| 浄土宗大本山光明寺【仏の教えを伝えるお寺】<外部リンク> | |
| 鎌倉観光公式ガイド内紹介 | 光明寺の紹介 |